冷え性の身体的要因チェックと内臓冷え性
冷え性を起こしている身体的な要因をチェックリストで確認してみましょう。
◆脳の温度が低い理由
①.脳の血流低下
②.耳あかがたまって温度計の赤外線が届かず正確に測れていないことがある
脳(鼓膜)の温度は、37度前後が正常(女性の高温期)ですが、
冷え性の方はそれよりも低いといわれています。
◆身体的要因
①.身体で熱が作れない
ダイエットによるカロリー摂取不足、運動不足で起きる筋肉量の低下など
四肢末端型や全身型に多い。
②.身体から熱が逃げやすい
皮下脂肪が薄い、皮膚血流が多く汗をかきやすいなど
内臓型、全身型に多い。
③.身体の熱を全身に運べない
うっ血や動脈硬化などから起きる血行障害により、体の隅々に血液が巡らず冷える
下半身型に多い。
◆身体的要因チェック 該当数がもっとも多いところがみなさんの身体的要因の原因となっています
1.身体で熱が作れない
・身体はどちらかというと細めだ
・手と足の先がいつも冷たい
・汗はほとんどかかない
・寒いと気分が憂鬱になる
・食事の量は少なめである
・冷えると頭痛がすることがある
2.身体から熱が逃げやすい
・太ももや二の腕が冷える
・自分では冷えを感じているのに手足を触ると温かい
・アレルギー体質である
・おなかが冷えやすい
・冷えるとお腹が張ったり痛くなる
・冷えると頭痛がすることがある
3.身体の熱を全身に運べない
・足や下半身は冷えるが手や上半身はそれほどでもない
・頭がのぼせたり顔や上半身がほてる
・特に顔や上半身に汗をかきやすい
・イライラしやすい
・おなかが冷えやすい
・冷えるとお腹が張ったり痛くなる
※熱が逃げやすい人は首や胸元にマフラーを巻く等風に当たらない保温が大切
伊藤剛先生(北里大学)が、以前取り上げた記事の中に脳温と冷え症に関連した記事がございましたのでご紹介します。
内臓型冷え性|世界一受けたい授業 8月7日
●内臓型冷え性の特徴は、仲は冷えているけど、外が温かいので、火照ったり、汗をかいたりする。
●内臓型冷え性が進むと、脳が冷える。
脳の機能も全般的に落ちるので、例えば、体がだるい、思考がまとまらないといった症状が出てくる。
耳型体温計で計測すると脳の温度がわかるそうです。(鼓膜の温度が脳温とほぼ同じ)
◆内臓型冷え性チェック
1 涼しいところにいるとお腹が冷えつらい
2 二の腕・ももが冷える
3 手の先・足の先は温かいのに冷えを感じる
1つでも当てはまれば内臓型冷え性の可能性あり。
1が当てはまる人は、元々冷えている内臓がさらに冷やされるため、症状が悪化したり、痛みが出たりなどする。
2が当てはまる人は、中心部の冷えが広がっているから。
3が当てはまる人は、手足の血管が開いたままで、血液の流れが良いため、熱が奪われていってしまう。同時に表面の血液の流れが良いので汗をかく。
自覚症状があるのはまだよいほう。中には内臓が冷えていても自覚していない方もおり、そちらの方が危険。
●体温を脇の下に挟み、10分間測ると、体の芯(内臓)の温度がわかる。
36度3分以下の場合、内臓型冷え性の可能性があるそうです。
※女性の方は低温期を避けて計測してください。
●内臓型冷え性を予防する方法
●内臓型冷え性を防ぐには、体の芯を温めることが一番。
・汗をかかない程度に厚着を心がける。
・お風呂にじっくり浸かる。
・ウォーキング(第2の心臓とも呼ばれるふくらはぎが動き、そのポンプ作用で血流が良くなる。また筋肉を使うことで体温が上がる。)
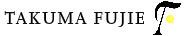



 前のページ へ
前のページ へ