低体温になるとなぜ不調を招くのか
低体温になると体にさまざまな不調を招くといわれていますが、その主な原因とは何なのでしょうか。
(2010/11/18、日経ウーマンより)
低体温になると様々な不調を招く。
その第一の理由は、「免疫力をつかさどる血液中のリンパ球の数が減るので、カゼなど様々な病気になりやすくなるから」と新潟大学大学院医歯学総合研究科の安保徹教授は指摘する。低体温になると疲れやすくなるのもそのためだ。
身体が低体温になると、免疫力が落ちるために風邪などにかかりやすく、また疲れやすくなります。
また、血の巡りが悪くなっているので、体中の細胞が必要とする栄養素や酸素をスムーズに運搬できない。そのため、体全体の機能が低下してしまう。
例えば、肌にはツヤがなく顔色も悪く、肩や首の凝りがひどくなる。体の内側では、胃や腸などあらゆる器官の働きが落ち、下痢、食欲減退などにつながる。体の中で働く酵素も37℃くらいで最も活性が高まるので、低体温ではその働きが落ちる。
また、血行が悪いために体の細胞が必要としている栄養素、酸素などが運搬できないため、体の機能が低下してしまうとのことです。
女性にとって怖いのは、低体温がホルモンバランスの崩れにつながるということだ。
「事実、不妊に悩む女性には低体温の人が多い。低体温が解消したら妊娠できたというケースも多い」とクリニックハイジーアの矢崎智子院長は指摘する。体温をコントロールする自律神経系とホルモン系は関わりが深く、自律神経の働きが乱れるとホルモンのバランスにも影響すると考えられる。
低体温によって、自律神経の働きが乱れてしまい、結果ホルモンバランスが崩れてしまう。
それにより、不妊に悩む人がとても増えているそうです。
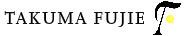



 前のページ へ
前のページ へ